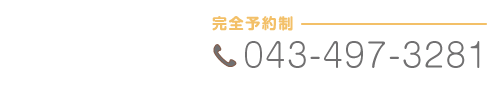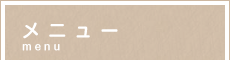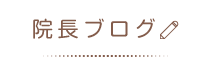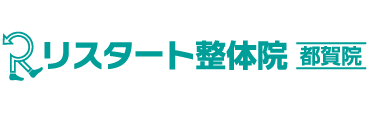体温調節のしくみとはたらき
人間の体温は外気温にかかわらず、健康であれば、常に36〜37度と一定に保たれています。
体温を一定に保つため、暑ければ熱を放出し、汗を出したり、寒ければ熱の放出を抑えるといった常に人間は体温調節をしています。
暑いときの体温調節
・気温が高かったり、運動などによって体温が上がると、体表近くの毛細血管が広がり、血流が増えて熱を放出し、汗が分泌され、その蒸発により、熱が奪われ、体温を下げています。
成人の場合
普通に生活しているだけでも皮膚からは1日に約600ml汗として出ています。
運動などをした場合の汗の量は2〜3リットルも汗として出ています。
寒いときの体温調節
・気温が低い時には、毛細血管が収縮し血流を減らし、熱の放出を抑えていきます。
肌が急な寒さを感じたときに、鳥肌をつくります。
これは、立毛筋(自分の意思で動かすことができず、鍛える事ができない筋肉)を収縮させて熱を産生し、体温を上げてくれています。
汗腺の種類とは?
汗を分泌する汗腺には、エクリン腺とアポクリン腺の2種類があります。
エクリン腺はほぼ全身に分布しています。
アポクリン腺は脇の下、陰部、乳頭部などの毛根部にしかなく、汗は細菌の影響を受けて特有のニオイを発します。
汗の種類とは?
暑い時にかく汗・・・温熱性発汗
緊張した時に手のひらや足の裏、わきの下にかく汗・・・精神性発汗
刺激の強いものを食べた時に顔面にかく汗・・・味覚性発汗
参考文献
しくみと病気がわかる
からだの事典